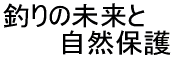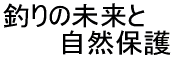外来魚バスターズでは、メンバー各々が休暇やわずかな時間を使った個人駆除を頻繁に行っており、その時の情報をもとに定例駆除のポイントが決定されます。夏の終わりからずっと駆除を続けているマキノ方面の漁港では、小型ながら数多くのバスが漁港内に集まってきている様子が報告されました。また、南小松方面の船溜りでは最近、中小型のバスが増加傾向にあるようです。そこで、今回の定例駆除では本隊をマキノ方面に置き、別働隊2名を南小松方面に派遣する体制で臨みました。
夜から降り続いていた雨も、日が昇る頃にはあがり、湖面からはもやが立ち込めます。私は防波堤のポイントに入り、エビを撒くと、小型のバスがうようよと集まってきました。そこで今日も、二本針フカセの仕掛けを使うことにします。
|
 |
 |
秋に入り駆除される外来魚の数が増えてきたので、私は釣った魚をいれるバッカンを二まわり大きいものに換えました。バッカンが一杯になると、気持ちもいっぱいいっぱいになり、駆除の効率が下がってくるからです。しかし今回は、数は釣れるもののほとんどが15cm程度のバスなので、釣れども釣れどもバッカンの中身が増えた気がしません。釣れば釣るほど、バスとともにストレスもたまってくる気がします。もはやこれは釣りではなく、単純作業でしかありません。この作業をいかにストレスなくこなすか、長く駆除を続けるためには技術だけでなく、精神面での工夫も必要となってきます。
今日は連休ということもあり、たくさんのバサーが来ています。滋賀県職員の方がやって来られ、一人一人にポケットティッシュを手渡していきます。琵琶湖ルール普及のためのお仕事のようです。
|
 |
 |
ふと横を見ると、数日前の個人駆除の折に見かけたバサーがいます。その時は、ルアーで小型のバスを結構釣り上げていましたが(もちろん釣ったバスは無造作に湖面に投げ捨てていました)、今日はほとんど釣れていないようです。最近のこの漁港には、バスとギルしか居らず、小型のバスは体高が高くヒレの鋭いギルを捕食することが出来ないので空腹状態にあり、ルアーにも反射的に食いつくことがあります。しかし、駆除を集中的に行ったことにより密度が急激に減ると(そうは言ってもまだたくさん居るのですが)、警戒してなかなか掛かりにくくなります。スレるという状態です。エビを生餌にした場合でも、これまでは餌をすぐに飲み込んだため体の奥の方に針が掛かっていたものが、今回は上顎の先端にしか、それもうまく合わせなければ掛からなくなっています。餌をくわえてもすぐには飲み込まなくなっているのでしょう。これでは、たとえルアーをくわえたとしてもすぐに吐き出しているのに違いありません。
10時半頃から、漁港はワカサギの水揚げでにぎやかになりました。今年は豊漁なのでしょうか。大きなトラック2台に次々と積み込まれていきます。琵琶湖では、ワカサギも国内の他の水系から導入された国内外来種です。この事をもって、ワカサギが移入されているのだからバス・ギルも居て構わない、とする意見があります。これは擁護派と言われる人々お得意の話のすり替えであり、もはや語る舌を持ちません。ただ、世間の人々がこのような屁理屈に惑わされないように、生物多様性の意義や外来生物の問題、それらと人の暮らしや文化などとのかかわりについて、自然科学、人文・社会科学的知見に基づいて学者や行政が啓発していく必要性は強く感じます。
|
 |
 |
ワカサギの水揚げが続く漁港内では、ワカサギの小さな群れがバス・ギルに追い立てられ、あっと言う間に壊滅される光景が見られました。何ともやり切れない現実でした。ただ1匹残ったワカサギを網ですくってみましたが、傷つき瀕死の状態です。このまま逃がしても生き残る可能性はありません。そこでこのワカサギを餌に、ワカサギを捕食していたバスを釣り上げ駆除することに成功しました。
|
 |
 |
昼食には、用事を済ませ昼前に駆除に駆けつけたメンバーお手製のおでんがふるまわれました。寒い季節には、あたたかい食事はたいへんありがたいものです。目の前では3羽のカモメが飛来し、水面上で羽ばたきながら魚をすくっています。バスが上層に浮いてきているのでしょう。漁港の外でも同じような光景が見られました。
|
 |
 |
午後も同じようにバスが連れ続きます。3時頃になると、ギルも混じり出します。20cm以上のギルが二本針に同時に掛かると、さすがに重さを感じます。が、そこは磯竿の馬力で見事に釣り上げます。今回また、変わった形のギルが釣れました。背びれの後部が三角形にえぐられています。鳥の嘴でくわえられた時の傷でしょうか。
一方,南小松方面では、今日も中小型のバスが大量に船溜りに入ってきているようです。別働隊2名のうち、一人は独特の胴付仕掛で深場を攻め、20〜30cm前後の比較的型の良いものを釣りあげていきました。もう一人は数で勝負と、足元に見える小型のバスを、エビを少量ずつ撒きながら琵琶湖浮きを使った浮き釣りで大量に駆除していきます。そのまま3時頃まで釣れ続き、結局30キロほどの駆除量となりました。
|
 |
 |
たくさんの獲物を手に、夕刻、別働隊のメンバーが本隊に合流しました。まだ釣り足りないのか、再び竿を出します。ちょうどこの頃、水面にたくさんの波紋が見られるようになりました。いつものギル時合いのようです。この後、釣れるのはギルばかりとなりました。
防波堤の外では、漁師の方が刺し網を入れています。外来魚を駆除するためのものです。刺し網では、一度に150kgを捕獲する時もあれば、まったく獲れない時もあるそうです。網にもスレるのでしょうか。網を行き止まりの通路のようにはりめぐらせる‘えり’を使っても、バスは胸鰭を器用に使って静止ばかりか反転もできるようで、一旦えりに入っても脱出してしまい、なかなか駆除できないそうです。一方、バスターズでは、10名弱の人数で50kg〜100kg以上の外来魚をコンスタントに駆除しており、一般市民による駆除の方法として釣りがいかに有効かがわかります。
|
 |
 |
今回は、型が小さいこともあり、2箇所での合計重量は73.6kgでした。しかしその数は1486匹と、大変なものでした。そのほとんどがバスです。バスの個体数を減少させていくには、成熟前の20cm以下の個体を大量に駆除することも効果的と考えられます。冬場には、小型とは言え大量に集まってくるバスを粘り強く駆除する必要があります。
これで今年の目標である3トンまであと100kgを切りました。本日奮闘いただきました9名の皆様、お疲れ様でした。
|
| ■ 駆除成果 |
| 参加人数 |
|
9名 |
|
|
| ブラックバス |
|
1266尾 |
|
61.1kg |
ブルーギル |
|
210尾 |
|
12.5kg |
|
|
| 合計 |
|
1476尾 |
|
73.6kg |
|
|