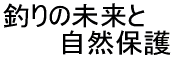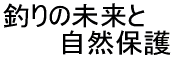今回の定例駆除も、引き続きマキノ方面で駆除を行いました。朝と昼の気温差が大きい時期になってきました。現場には、日出の少し前に到着しましたが、かなり肌寒く、十分着込んでの活動になります。
現場全体の様子を見て回ると、船の下にはすでに多くの外来魚の姿が見えます。水面に仕掛けを投入すると、いつもと変わらぬ早さで、外来魚が食いついてきます。今日も外来魚の魚影はかなり濃いようです。今日も20センチクラスの大型ギルが釣り上がってきます。
大型ギルは、同じ場所で釣り続けるとしばらく姿を消しますが、少し経つとまた釣れだします。その数はすさまじく、休憩する間もないほどです。外湖から入ってきているのでしょうが、いったいどこから集まってきているのかと思いたくなるほどです。周辺の沖には、藻場が広がっているのでそこからやってきているのでしょう。一方で、ブルーギルが20センチにまで生長するのに一般に5年以上かかることを考慮すると、数年に渡って駆除を続けているこの現場では、居着きの個体はすでに壊滅しているとも考えられます。ブルーギルの移動力は見ている限りあまり大きいようには思えませんが、時間をかけて案外遠いところからも集まってきているのかもしれません。結局、このポイントでは朝から夕方まで、休むことなく延々と大型ギルが釣れ続いていました。
|
 |
 |
今日はバスとギルの居場所が、かなりはっきりと分かれていました。前回に比べて、バスの数が増えています。15センチ前後のバスが多いですが、たまに30センチ後半の大型ものもいます。暑い時期はブルーギルの活性が高いですが、気温が低くなり、秋が始まる頃から徐々にバスの活性が高くなっていきます。ちょうど今の時期が入れ替わりの季節といえます。バスは盛んにエサを追っていました。
|
 |
 |
今日は、これに加えて、たくさんの在来魚の群れが見えます。ウグイのようです。8月後半以来、ここでは、以前と比べて在来魚が多く見られるようになってきましたが、これほど大量に見られたことはありません。
|
 |
 |
ウグイは10数匹の群れを作り、移動していました。中には、群れを作らずに一匹だけで泳いでいるものもいました。よく見ると、ふらふらと力無く泳いでいます。バスやギルにかじられ傷ついたために、群れについていけなくなったようです。このような手負いのウグイが何匹も見られました。群れウグイの周りにもバスが集まっており、スキを見ては攻撃を繰り返していました。
|
 |
 |
ウグイの群れの他、鮎玉が見られました。直径2メートル以上はあろうかという巨大な鮎玉です。その数は何百匹にも及ぶでしょう。私は今まで鮎玉をあまり見たことがなかったのですが、これはなかなか感動的なものでした。しかし、この鮎玉もバスに狙われていました。水面近くを移動する鮎玉をバスが底から狙っていて、時折攻撃を加えていました。魚食性のバスにとっては、小型のコイ科やアユなどは格好のエサとなります。これに一計を案じ、この在来魚群れの周りに仕掛けを投げ込む作戦に出ます。すると、底で在来魚を狙っていたバスが、活きエビにまんまと食いついてきました(^_^)V。この作戦で、次々とバスを釣りあげることができました。本来この現場は魚類が集まりやすい場所といえると思います。地元の漁師さんの話によると、以前はたくさんのスジエビがとれたそうで、一晩でタツベがいっぱいになったと聞きます。ですが、見る影もありません。獰猛な外来魚がこれだけいれば、他の生物などいられるはずもありません。昔はフナがたくさんいた、コイがよく釣れた、と言われていた場所が、現在はよく知られたバススポットとなっている話を他にもたくさん聞きます。以前、モロコがたくさん釣れた場所に久しぶりにいってみたら外来魚ばかりでショックを受けた、などという話は枚挙に暇がありません。かつては在来魚の重要な住処だった場所を、バス・ギルが確実に追詰めていったのです。
逆に、この様な場所では外来魚を集中的に叩くことができ、また在来魚への効果も高いといえます。外来魚駆除活動も最大限の効果を上げるために、戦略的に進めることが重要といえます。
|
 |
 |
早朝こそ寒かったものの、日が昇ってからは気温も上がり、天候にも恵まれました。今回は、前回まで大半を占めていたギルをバスが上回り、合計91キロ、1427尾の戦果を上げることができました。秋のけはいを感じてか、バスの活性が高くなる傾向が見られ、これからの季節は大量駆除も予想されます。本日、ご奮闘頂きました10名の皆さんお疲れ様でした。
|
| ■ 駆除成果 |
| 参加人数 |
|
10名 |
|
|
| ブラックバス |
|
825尾 |
|
61.0kg |
ブルーギル |
|
602尾 |
|
30.0kg |
|
|
| 合計 |
|
1427尾 |
|
91.0kg |
| |
|